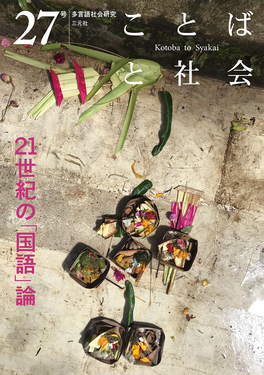內容簡介
內容簡介 「国語」には、前世紀後半から、国内の人々が用いることばとそこにある多様性と、どのように向き合うべきかという問いが投げかけられるようになった。21世紀も早や四半世紀を迎えた今日、オンラインでのコミュニケーション、グローバルな覇権的言語圏、各種言語法の整備など、拡張する「国語」を取り巻く時代状況が、その思想や概念をいかに変容させているのかを考える。■巻頭コラム「「いのち輝く未来社会」はデザインできたか?」柿原武史■特集:21世紀の「国語」論[序論]「21世紀における「国語」再考」藤井久美子「ルクセンブルクを代表する言語とは何か――移民による社会の多言語化と国語としてのルクセンブルク語の位置づけ」小川敦「2つの「国語」を持つ国シンガポール――多民族多言語都市国家の言語政策とその変遷」 奥村みさ「「国語」インドネシア語の現在(いま)」中谷潤子「サハラ以南アフリカにおける「『国語』の不在 未完」再考」沓掛沙弥香「「国語」と「やさしい日本語」と――二つの「正しさ」による軋轢と葛藤」東弘子[報告]「明晴学園の「国語」――「手話」と「日本語」」狩野桂子・岡典栄[コラム]「亡霊たちの住まう城――フランス語国際センター訪問記」佐野直子[特集あとがき]「『国語学辞典』類の「国語」記述から」安田敏朗■投稿論文[研究ノート]「1930年代の在日朝鮮人商店名・企業名について――京阪神を中心に」宋実成■書評西島佑(著)『「国家語」という思想――多言語主義か言語法の暴力か』 評者:吉田真悟楊一林(著)『同調行動のエスノメソドロジー――日中ビジネスコミュニケーションの異同』評者:バギルリ・ナルギズ金澤貴之・二神麗子(著)『手話の法制化と聾者の言語権――そのポリティクスと課題解決への視座』 評者:シルバ・グレイス■連載報告 多言語社会ニッポン琉球弧の言語:「シマクトゥバへの思い」石原昌英移民の言語:「アフガニスタン人女性難民の日本社会適応――言語環境の視点から」アキバリ・フーリエ手話:「コーダの手話継承から考える「手話」」安東明珠花■近刊短評 オンラインによるコミュニケーションの拡張など、今日的な時代状況が「国語」の思想や概念をいかに変容させているのかを考える。