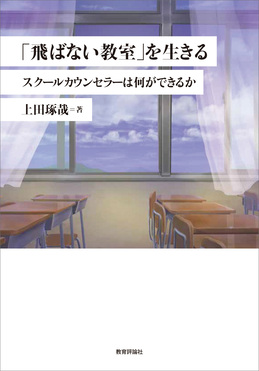內容簡介
內容簡介 ベテランカウンセラーでもある著者が、学校の日常を物語に仕立て、子ども・教師・カウンセラーの視点からリアルな学校の姿を紹介。全体像が見えにくい“深い森”のような「学校臨床」を案内する。□本書の狙いと語り方 本書は教育現場で起こるさまざまな問題に取り組んでいる人たちへ向けて、学校臨床という活動の実際とその可能性を知ってもらうことを目的としている。 筆者はこれまで幸いなことに、区立の教育相談室、公立中学校や高等専門学校、また私立大学の学生相談室などでカウンセラーの仕事をしてきた。そこで、子どもや若者たち、その保護者、さらには教職員のお話を聞いてきた。そのような経験をふまえて「学校臨床の森」の実際を伝えることができるだろう。本書では学校臨床のリアルを感じてもらうために、ある語り方を採っている。それは学校臨床の実際を、それぞれの人物の「私の物語」として語るということである。 学校臨床というのは目の前の「個」(すなわち「私」)を重視する態度を特徴としている。例えば、不登校という現象について考えるとき、さまざまな制度改革、家庭環境へのアプローチやクラス運営の工夫といった全体あるいはシステムへ向けた対応が思いつくだろうが、学校臨床にたずさわる者はあくまで「学校に行きたくない」と言っている目の前の子の話を聞こうとするだろう。そして「学校に行けない」とその子が言うとき、それを他者に伝えようとすれば、(単なる情報ではなく)必ず「私の物語」になるのである。ゆえに、不登校も個別の物語として理解しようとする姿勢が大切になる。 本書の場合、「私の物語」とはまず、ある一人の子どもが語り手となる物語と考えることができる。ただし、本書はそれだけでなく、その子どもにかかわる教師もスクールカウンセラーも等しく「私の物語」をもっているとみる。そして、それら別々の「私の物語」同士のかかわりとして学校臨床を理解してみようと試みるものである。すなわち、森に住んでいる特定のいきもの目線で描いたものを複数重ね合わせることで、その森全体が理解されるように。 本書では、まず前半にそのガイド役に登場してもらう。すなわち、学校臨床の主な当事者である「ある子ども」「ある先生」「あるスクールカウンセラー」を登場させ、それぞれの日々の悩みや戸惑いを描写しながら、三人がどういう人物であるかを紹介する。それをふまえて、後半は学校という舞台の上で彼ら三人がかかわる日常を描いていく。言い換えるならば、本書は三人の「私の物語」が交差するなかで学校臨床の森を立体的に理解してもらうことを目指している。(略) また「私の物語」をそのまま記述するだけでは学校臨床という実践の意義が十分には理解しづらいと思われるために、臨床心理学的な解説も折々に加えてある。それによって、見えているようで見えていなかったもの、すなわち「学校臨床の森」が(特にその豊かさが)可視化されるであろう。 結果としてそれは、「飛ばない教室」をわれわれが生き延びる知恵となるはずである。(「はじめに」より) ベテランカウンセラーでもある著者が、学校の日常を物語に仕立て、あまり知られていない「学校臨床」の姿を案内する