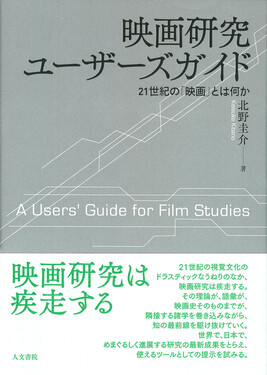內容簡介
內容簡介 映画研究は疾走する21世紀の視覚文化のドラスティックなうねりのなか、映画研究は疾走する。その理論が、語彙が、映画史そのものまでが、隣接する諸学を巻き込みながら、知の最前線を駆け抜けていく。世界で、日本で、めまぐるしく進展する研究の最新成果をとらえ、使えるツールとしての提示を試みる。◎目次はじめに 映画を未来時制からアプローチする第1部第1章 「映画とは何か」という問いを再起動する (1)芸術、技術、資本の交差点 (2)「映画とは何か」という問いを再起動する (3)《質的特徴》、《歴史的文脈》、《制作意図》から接近してみる第2章 映画の生態系 (1)「映画とは何であったのか」――歴史のなかの映画か、映画による歴史か (2)映画の生態系 (3)学説史をリセッティングする第3章 映画の地層分析 (1)映画作品(film)なのか、映画体験(cinema)なのか (2)ハリウッド映画の主体は誰か (3)外部からのハリウッド映画論――作家と映画館のあいだ第4章 「作家」は唯名論か (1)「作家」はどのように映画史に登場したのか (2)「作家主義」と「作家の死」 (3)それでも「作家」は死なない第5章 技術はどこまで物体か (1)作家主義以降の技術経験論――技術の効果 (2)デジタル生態系における進化型 (3)「アトラクション」は効果か、それとも表現か第6章 知覚機械としての映画 (1)アニメにおけるモーション効果と映画による運動表現 (2)日常の感覚作用に訴える映画 (3)知覚機械としての映画第2部第7章 カラー (1)映画史におけるカラーを再考する (2)カラーのテクノロジーから、色彩意識の登場へ (3)ヒッチコック映画のカラー、あるいは近代における投影の進化第8章 映画が放つホラー (1)ヤバイホラー映画、ヤバいホラー映画研究 (2)技術の不気味 (3)ホラーのサウンド、カラー、デジタル< 21世紀の視覚文化のドラスティックなうねりのなか、映画研究の最新成果をとらえ、使えるツールとしての提示を試みる。
作者介紹
作者介紹 北野圭介【著者】北野 圭介(きたの・けいすけ)1963年生。ニューヨーク大学大学院映画研究科博士課程中途退学。ニューヨーク大学教員、新潟大学人文学部助教授を経て、現在、立命館大学映像学部教授。映画・映像理論、メディア論。ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ、ラサール芸術大学(シンガポール)、ハーバード大学ライシャワー研究所などで客員研究員をつとめる。著書に『ハリウッド100年史講義』(2001年 新版2017年)、『日本映画はアメリカでどう観られてきたか』(2005年)、『大人のための「ローマの休日」講義』(2007 年、以上、平凡社新書)、『映像論序説』(2009年)、『制御と社会』(2014年)、『ポスト・アートセオリーズ』(2021年、以上、人文書院)、『情報哲学入門』(講談社選書メチエ、2024年)。編著に『映像と批評ecce[エチェ]』1~3 号(2009年~ 2012年、森話社)、『マテリアル・セオリーズ』(人文書院、2018年)。訳書にD・ボードウェル、K・トンプソン『フィルム・アート』(共訳、名古屋大学出版会、2007年)、アレクサンダー・R・ギャロウェイ『プ